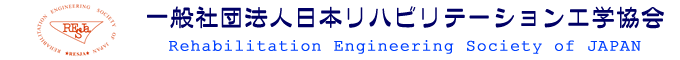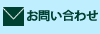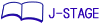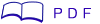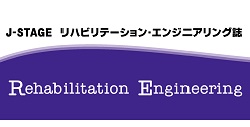����ŐV��Vol.39/ No.2 (�ʊ�134��)
���W�u���n�r���e�[�V�����̈�ɂ����� �E�F�A���u���E�m���E�F�A���u���f�o�C�X�̊��p�v

���W�ɂ������ā@�u���n�r���e�[�V�����̈�ɂ�����E�F�A���u���E�m���E�F�A���u���f�o�C�X�̊��p�v�@�R�{�@�B��
���n�r���e�[�V�����̈�ɂ�����E�F�A���u���f�o�C�X�ƃm���E�F�A���u���f�o�C�X�̊��p�́A�ߔN�}���ɔ��W���Ă���B�f�o�C�X�̐i���ɔ����A����܂Ő��l�����������������ł���悤�ɂȂ�A����炪�Z���s�X�g�A�����ҁA�Ƒ����܂ނ��ׂĂ̊W�҂Ƀv���X�ɂȂ邱�Ƃ����҂���Ă���B����̓��W�ł́A�E�F�A���u���f�o�C�X�E�m���E�F�A���u���f�o�C�X�̏Љ�⊈�p���@�A�J���Ƃ��̉\���ɂ��đ��p�I�ɒT������B
���n�r���e�[�V�����ɂ����鐇������E�F�A���u���f�o�C�X�̊��p�@�쓇�@�K���Y�A �����@�ȑ��A �R���@�q�j
�E�F�A���u���f�o�C�X�̔��W�ɂ��A�����������܂ޗl�X�Ȋ����f�[�^�̎擾���e�ՂɂȂ����B�{�e�ł́A���������v�����\�ȃE�F�A���u���f�o�C�X���Љ�A�������������n�r���e�[�V�����ɗ^����e���ɂ��čŐV�̒m�����T������B�]���̃��n�r���e�[�V�����ł͐��������̕]�����\���łȂ��������A�����̎��͓����̐g�̊�����^���w�K�ɑ傫�ȉe����^����B���������āA���n�r���e�[�V�����̌��ʂ��ő剻����ɂ́A�E�F�A���u���f�o�C�X��p�������������̐��m�ȕ]���ƃA�v���[�`���s���ł���B�{�e�ł́A���n�r���e�[�V��������ɂ����鐇�������v���̐V���ȉ\����T��B
�����Z���T�����^���@�ؕ�@�M��
�w���X�P�A��ړI�Ƃ����E�F�A���u���f�o�C�X�̕��y���ڊo�܂�������A���^�����Z���T�����{�̈�É��̈�ŕ��y���Ă��Ă���B�{�e�ł̓}�b�g���X�̉��ɐݒu����x�b�h�ݒu�^�����Z���T�ɂ��ďЉ��B�x�b�h�^�����Z���T�ł͐����E�o���ɉ����ė����̏��邱�Ƃ��ł���ƂƂ��ɁA��������ɔ������S�����Ȃ��̂ŁA���P�ʂ�N
�P�ʂ̑�����e�ՂɂȂ�ƍl������B��É��{�݂ł̕��y�ƂƂ��Ɍ������ʂ̂���
�Ȃ�~�ς����҂����B
�E�F�A���u���E�m���E�F�A���u���f�o�C�X�����p�����������Y���]���Ƃ��̉��p�@�v�ā@�T
�E�F�A���u���E�m���E�F�A���u���f�o�C�X�̗Տ����p�͌v���p�f�o�C�X�^�p�A�v���f�[�^�Ǘ�����ёΏێ҂ւ̌��ʃt�B�[�h�o�b�N�Ƃ����_����L�p�ł���ƕM�҂͍l���Ă���B�����āA�����̃f�o�C�X�����p�����������Y���]���́A�C���^�[�l�b�g�ڑ�����Ă���X�}�[�g�t�H����^�u���b�g�[���ƕ��p���邱�Ƃɂ���āA�����ҁE�Տ��Ƃ���ёΏێ҂̑o���ɑ��ėL�v�ȃc�[���ƂȂ邱�Ƃ�������҂����B�{�e�ł́A�E�F�A���u���f�o�C�X��p�����������Y���]���̎��ۂƃE�F�A���u���E�m���E�F�A���u���f�o�C�X�����p�����������Y���]���Ƃ��̉��p�ɂ��ďq�ׂ�B
���{�݂�ICT���̎��g�݂ɂ��ā@����@��
���q����ɂ��A�������É��T�[�r�X�̎��v�����傷�����ŁA�l�ޕs�����[�������Ă���B���ƊE�ł́A�@���l�ޕs���A�A����ƕ��S����A�B��샌�x���ቺ���o�c�ۑ�ƂȂ��Ă���B���̉�����Ƃ��āA���e�N�m���W�[�̓�����ICT�����i�߂��A��ƕ��S���y�����A����҂ƒ��ڊւ�����Ƃɗ]�T�������đΉ����邱�ƂŁA��쌻��S�̂̐��Y�������ڎw���Ă���B�{�e�ł́A��쌻��ɂ�����ICT����ʂ���������ُ팟�o�E�ʒm�V�X�e���A�f�[�^���p���@�ɂ��Ă̎��g�݂��q�ׂ�ƂƂ��ɁA���e�N�m���W�[�̉ۑ�ƌ��E�ɂ��čl�@����B
�����Z���T�[�����̎��g�݁@�V���@�E��
��쌻��ł́A�����F�m�ǂ̐i�s�ɂ��Ή���������p�҂��������A�E���̕��S�d�x����l�ޕs�����ۑ�ƂȂ��Ă���B�V�l�ی��{�݁u���n�r���Z���^�[����݁v�ł́AICT�@��̓�����i�߂Ă���B�{�e�ł́A���{�݂œ������Ă���u����SCAN�v����сu�V���G�b�g�����Z���T�v�̓�������Ɗ��p�ɂ��ďq�ׂ�ƂƂ��ɁA�u���n�r���Z���^�[����݁v�ɂ������̓I�Ȏ��g�݂ɂ��ďЉ��B�����āA��쌻��ɂ�����ICT�����̉ۑ�ƓW�]�ɂ��ďq�ׂĂ����B
��ԔF�m�ۑ�ɑ��鎩���I�ړ��x�����@�ɂ��ā@�`LOOVIC �̊J���Ɏ��������������Ƃ��̎�g�݁`�@�R���@��
�u�����v�Ƃ����l�Ԃ̊�{����́A�Љ�I�E�����I�~���������߂̈ړ���i�ł���B�ړ��̐�Ɍ����Ă�����ʂ́A�l�̗~���̋����ɂ��قȂ�B��ԔF�m�̉e����\�́A���E���قȔ͈͂͌l�ɂ���ĈقȂ邪�A�ł�����苤�ʂ����A�v���[�`���@�ł̉������]�܂��B�{�e�ł́A��ԔF�m�ɖ��������Ώێ҂ւ̈ړ��x���e�N�m���W�[�ł���uLOOVIC�v�ɂ��āA�J���Ɏ��������������Ǝ��g�݂��Љ��ƂƂ��ɁA����̓W�]�ɂ��ďq�ׂĂ����B
�N���Z���T�[�@�����@�݂���
���{�̍������29.0���ɒB���A��Q�҂̍�����i�s���Ă���B���t�{�̒����i2013�j�ł́A�ݑ���ɂ����ĉ��҂��ł���J������e�Ƃ��Ĕr���i�r�����̕t���Y���₨�ނ̌����j���ŏ�ʂɋ������Ă���B�������A�r�����̕��S�y����r�������̂��߂̋@��ނ͏\���Ƃ͌����Ȃ�����ɂ���B�{�e�ł́A�r���g���u���́u�\�h�v�u���Áv�u�Ώ��i�P�A�j�v�̏d�v����`���鋦��F�莑�i�ł���R���`�l���X�A�h�o�C�U�[�ł���M�҂̗��ꂩ��A�r���Ɋ֘A����Z���T�[�A�����N���Z���T�[���Љ��ƂƂ��ɁA�r�A�����x���Ɋւ��鐧�x�̓����⍡��̓W�]�ɂ��čl�@����B