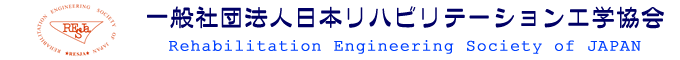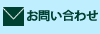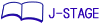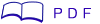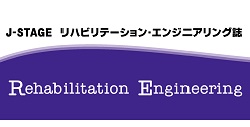協会誌最新号Vol.38/ No.1 (通巻129号)
特集「高齢者の移動を支援する用具について」
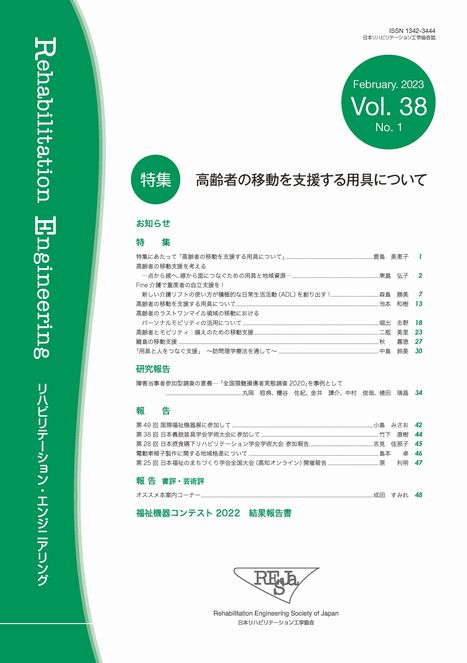
「高齢者の移動を支援する用具について」 鹿島 美恵子
現在、高齢者の移動支援には様々な用具が活用されていますが、安全で効果的な用具の活用のためには、機能性やデザイン性のある用具の発展、高齢者の移動の現状把握、人と用具をつなぐ支援等が必要だと考えられます。本特集では、高齢者の移動や移動を支える用具、高齢者と用具をつなぐ関わり等について取り上げています。様々な立場の方が高齢者の移動について考えると同時に、将来、誰もが経験する可能性がある身近な課題として、より多くの方が高齢者の移動について考える機会となれば幸いです。
「高齢者の移動支援を考える―点から線へ、線から面につなぐための用具と地域資源―」 東畠 弘子
「高齢者が生活していく中で、移動の問題は、在宅生活の継続に直結します。・・・高齢者一人ひとりに目を向ければ、その移動能力によって、自宅内の移動が困難であったり、外出はできてもここまでしか歩けないなど、それぞれです。・・・しかし、移動に困難があったとき、「何を用いて、(誰が) どのように、支援するのか」、ということは、高齢者を取り巻く関係者共通の課題であり、広い視点で考える必要があると思うのです。本稿で筆者は、個々の高齢者から、地域全体迄、個別福祉用具から、ソーシャルサービスまで、横断的に支える必要性について、私見ではありますが述べてみたいと思います。」
「Fine介護で重度者の自立支援を! 新しい介護リフトの使い方が積極的な日常生活活動 (ADL)を創り出す!」 森島 勝美
「平成9年(1997年)介護保険法が制定され・・・第1条には要介護者の尊厳を保持し自立した日常生活を営むことが明記されている。にもかかわらず、これらの要望に応えきれていない現状がある。特に重度の要介護者にとっての自立支援機器の開発は遅れていると言わざるを得ない。我々は、介護リフトを使った中重度者向けの移動・移乗・歩行のための自立支援機器の開発を進め、いくつかの製品と使用方法を開発したのでここに紹介する。」
「高齢者の移動を支援する用具について」 池本 和樹
「介護保険の介護予防・居宅サービスにおける福祉用具貸与の受給者数は、居宅介護支援に次いで2番目に多く、一方、介護保険給付費でみれば全体の約7%とされる。福祉用具は利用者が比較的に多い中でコストは抑えられており、かつ自立支援と介護負担軽減に大きく貢献しているといえる。しかしながら、福祉用具の使用時の事故・ヒヤリハットは今もなお多く発生している。今回は福祉用具の中でも高齢者の屋外移動をサポートする3つの用具について、それぞれの適合と使用上の注意点について説明する。」
「高齢者のラストワンマイル領域の移動におけるパーソナルモビリティの活用について」 堀出 志野
「日本では、75歳以上の高齢者のうち、過半数が500mを超えて歩行することが困難であるというデータがある。500m というのは、いわゆるラストワンマイルに満たない、徒歩7分程度の距離だ。・・・ところが、これまでラストワンマイル領域における移動手段の選択肢は限られ・・・なかでも自動車は、依然として多くの人にとって欠かせない移動手段であり・・・こういった状況のなかで、免許返納後の移動手段、いわゆる「代替モビリティ」のひとつとして期待されているのが、パーソナルモビリティだ。」
「高齢者とモビリティ : 備えのための移動支援」 二瓶 美里
「高齢期の移動活動は・・・自動車の運転断念、歩行困難など活動範囲を狭くする方向へと進んでいくことが多い。これらの制限を解消する可能性があるものとして、移動や移動支援のための技術がある。 ・・・一方で、高齢期において、移動に支援が必要となってからでは、こういった機器やサービスの情報を入手し、活用して生活に応用していくことは、言うほど簡単ではない。多様で常に変化する高齢期において、各々の望む形での暮らしを支えるには、どのような方法があるだろうか。本稿では、高齢者の移動活動の実態と、移動を支援する技術を紹介し、 さまざまな技術を活用し、個々人が豊かな高齢期を楽しむ方法について検討したい。」
「離島の移動支援」 秋 嘉徳
「鹿児島県には約600もの島があり・・・屋久島と奄美大島の間に、7つの有人島 (口之島、中之島、諏訪之瀬島、平島、悪石島、小宝島、宝島)と5つの無人島からなるトカラ列島があり、人口約650人の十島村がある。十島村との往来は、鹿児島市から各有人島を巡り、名瀬市までを結ぶ週に2回のフェリー航路のみで、1往復にかかる日数は、船中泊を入れて2泊3日の行程を要する。 一度フェリーを降りると、島間を行き来するのは、フェリーとは別の小さな高速船を利用するほかない。」
「用具と人をつなぐ支援〜訪問理学療法を通して〜」 中島 鈴美
「近年、障害者や高齢者が使用する福祉機器はITを駆使したものなど目覚ましく発展している。 一方、用具を使う障害者や高齢者は、 「杖や車椅子を使うようにはなりたくない」 「用具は安心して使えない」など抵抗感を持つ方も多い。筆者は、長年、障害のある方への生活期における理学療法にかかわっている。その経験の中で、機能など状態にかかわらず、使う人の生活歴、価値観などを配慮し、新たな環境や役割を提供し、本人の心理面の変化を見ながら、本人の目的や希望を実現する上で必要と考える用具の助言を行っている。今回、訪問理学療法の経験を通して、本人の気持ちや目標による行動の変化と福祉用具の活用について考える。」