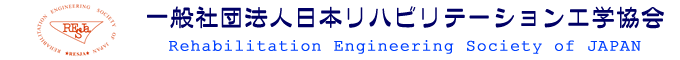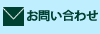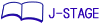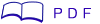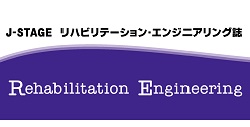協会誌最新号Vol.35/ No.4 (通巻120号)
特集「新しいリハビリテーション領域と機器」
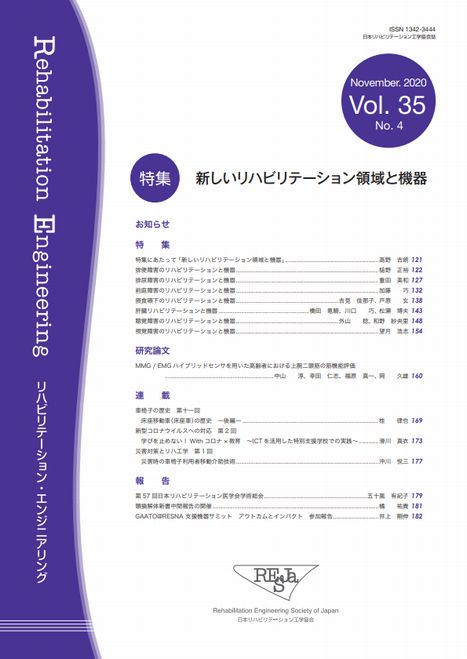
「新しいリハビリテーション領域と機器」の特集になります。
「排便障害」「排尿障害」「前庭障害」「摂食嚥下障害」「肝臓疾患」「聴覚障害」「視覚障害」と新しい領域で取り組まれているリハビリテーションの内容と使われている医療・介護機器が詳細に解説されています。特に今回はJ-STAGE上では内容の一部が動画で視聴できますので、ぜひご覧ください(編集委員 高野)。
「新しいリハビリテーション領域と機器」 Novel rehabilitation fields and devices 高野 吉朗
「昭和40 年代から始まった黎明期においては、運動器疾患や中枢神経疾患の後療法が主でした。ところが、現代のリハ医療の対象疾患は、循環器・呼吸器疾患などの内科疾患からがん疾患まで扱われるようになりました。」
「排便障害のリハビリテーションと機器」 槌野 正裕
「1日に2 回排便を行う人は、80 年の人生の中で1 年以上も排便に関連する時間を過ごしていることになる。人生の中での短い時間ではあるが、その排便に関連した一連の動作が障害されると強いストレスを感じて日常を過ごすことになるであろう。・・・。自分の目で直視することが出来ない直腸肛門の運動機能に対して、筋電図や内圧計、バルーン等を用いることで、患者に適切な運動指導を行うことが出来るようになる。」
「排尿障害のリハビリテーションと機器」 重田 美和
「・・・機器を通して筋の動きをモニタリングし、その情報を患者自身が目や耳で確認しながら骨盤底筋群を制御することを可能にする。」
「前庭障害のリハビリテーションと機器」 加藤 巧
「従来はハイテク機器で提示していた視覚刺激を誰もが持っているスマートフォンやタブレットで視聴できる動画やアプリが作成されている。一方IT の発展により仮想現実(Virtual Reality 以下、VR)やバイオフィードバックといったハイテク機器の臨床応用が期待されており、前庭リハビリはリハビリテーション工学の観点からも興味深い分野の一つと言える。」
「摂食嚥下のリハビリテーションと機器」 吉見 佳那子、戸原 玄
「・・・患者や家族の「食べる楽しみ」を支えることが、摂食嚥下リハビリテーションの本質であり、患者の生活の質(QOL:quality of life)の向上にもつながると考える。本章では、摂食嚥下リハビリテーションの診断、治療に用いられる機器に加え、摂食嚥下障害患者の食べる楽しみを支える最新機器、近年の研究成果を紹介する。」
「肝臓リハビリテーションと機器」 橋田 竜騎、川口 巧、松瀬 博夫
「・・・。入院中のがんリハビリテーションプログラムが、肝がん患者の骨格筋減少予防に有効なことが証明された。・・・。NAFLD 患者にひざトレーナーを使用することで、通常の歩行よりもより効率的に糖代謝を改善させる可能性がある。」
「聴覚障害のリハビリテーションと機器」 外山 稔、和野 紗央里
「難聴による日常生活や社会生活への影響、認知症発症のリスクを考慮すると、補聴手段の早期検討および聴覚補償機器装用による聴覚リハビリテーションは極めて重要である。」
「視覚障害のリハビリテーションと機器」 望月 浩志
「白杖や拡大鏡、遮光眼鏡などに加えて、近年発展が目覚ましいIT(information technology、情報技術)や映像技術などを利用したロービジョンケアデバイスが開発されており、今後さらなる技術の発展が見込まれる。」