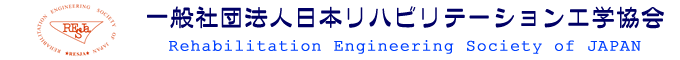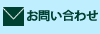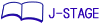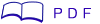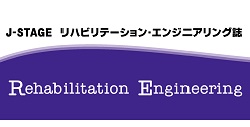協会誌Vol.31/ No.2 (通巻102号)
特集「Festina Lente! ゆっくり急げ ー急性期にしかできない支援ー」
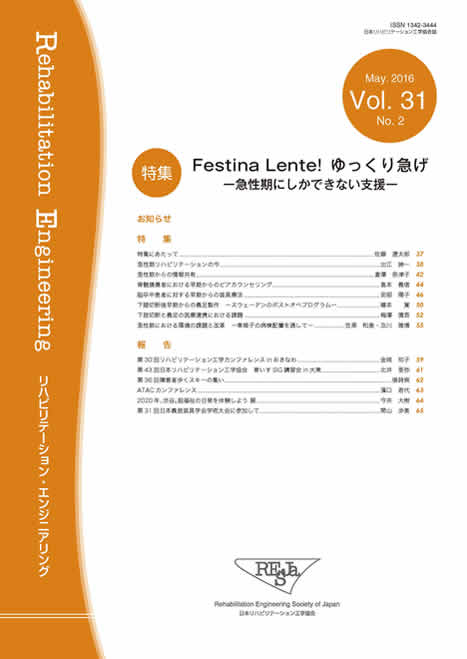
特集「Festina Lente! ゆっくり急げ 急性期にしかできない支援」をご紹介します。
「特集にあたって」 佐藤 遼太郎
「「Festina Lente(フェスティーナ・レンテ)」、これはラテン語で“ゆっくり急げ”という意味です。」 「急性期リハビリテーションの今」 出江 紳一 「脳卒中の急性期リハは、神経損傷を最小限に留め、合併症を管理(予防)しながら、ADL(活動)の改善を第一に目指す過程である。そのため、回復不良の上肢麻痺の訓練に費やせる時間は制限され、非麻痺側上肢を使ったADL の獲得が優先される場合が多く、それがlearned nonuse につながっている。」
「急性期からの情報共有」 倉澤 奈津子
「最近、NPO に参加している方から興味深いリハビリの話を耳にしました。鏡などを使い視覚から脳をだますことで幻肢痛の緩和が期待できるのであれば、義手を付けることも同じとの考えを元に、手や腕の代わりになる簡易的な義手で早急にリハビリを開始したところ、約1年で痛みが少しずつ弱くなってきたというのです。」
「脊髄損傷者における早期からのピアカウンセリング」 島本 義信
「家族との生活を先延ばしにされ気力を無くしかけたころ、リハの担当医から頸損連の当事者を紹介してもらい夫婦で話をした。ホームヘルプや訪問看護、移動支援などの社会的な支援があり重度の四肢麻痺の障害者であってもひとり暮らしをしていることを教えてもらった。このことは八方塞の中でもがいていた私たち夫婦には一筋の光明だった。」
「脳卒中患者に対する早期からの装具療法」 安部 陽子
「超急性期は基本的にベッドサイドで行うため、ベッドにて端座位をとる。褥瘡予防のためエアマットが使用されていることがあるが、これでは座面が柔らかすぎ座面からの刺激が不十分で、滑り落ちるリスクもある(図2-1)。そこで小型の昇降台を用いる。座面を高く設定するとKAFO の膝伸展位で体幹をアップライトに誘導でき、図2-2 のように背面を壁付けにすると、端座位保持の不可能な方が座位を保ち頭部挙上も可能となる。さらに、介助者が背後に回り後方から抱えて立位をとることも容易となる。」
「下腿切断後早期からの義足製作ースウェーデンのポストオペプログラムー」 橋本 寛
「一般的に義肢製作所が病院を訪問し、義足の製作適合を行う場合、訓練用義足の採型から適合=歩行訓練開始まで、一週間程度の時間を必要とする。MSS* は病院内で、採型から装着まで約2時間と驚異的に早い。義足製作を待つ必要がなくなり、その分だけ早期リハビリが図れる。」 *掲載注:MSS(Modular socket system)
「下肢切断と義足の医療連携における課題」 梅澤 慎吾
「筆者所属の義肢装具サポートセンター(以下:SC)の調べでは、過去一年間に歩行自立を果たしたリハ対象の下肢切断者61 名のうち、前病院から紹介のない例が21 名、約1/3 に相当する。更にこのうち11名は義足を着けていなかったことが分かっている。21 名はWeb 情報、TV 番組、親類や知人の紹介で受診に至っている。」
「急性期における環境の課題と改革ー車椅子の病棟配置を通してー」 笠原 和美 及川 雅博
「各病棟の看護師が車椅子を使用する際どのように区分し、また使いやすさ使いにくさ等どのように感じているかアンケートを実施した(2016.2.19 〜 2.26 実施 配布各病棟10 回収28/30)。アンケートは種類と配置数について質問した。
(1)配置数について 車椅子の種類別については脳外科病棟ではティルトリクライニング型が、整形外科病棟ではエレベーティング型が足りないという意見があった。クッションについては種類による用途がよくわからないという意見があった。」