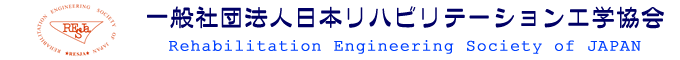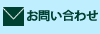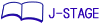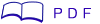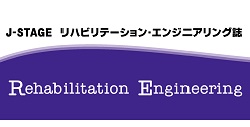協会誌Vol.31/ No.1 (通巻101号)
特集「私たちのいきる道−障がいを笑涯に−」
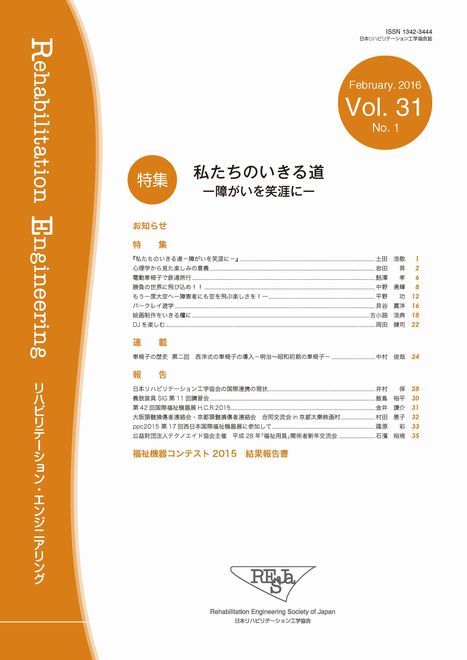
特集 「私たちのいきる道−障がいを笑涯に−」をご紹介します。
「私たちのいきる道−障がいを笑涯に−」
土田 浩敬
「母から“口に筆をくわえて、以前好きだった絵を描いてみてはどうか”と言われ、試しに口に筆をくわえて絵を描き始めることに挑戦しました。すると、私の絵を見た方から“凄く上手ですね”とお褒めの言葉を頂くようになりました。絵を描いていると、だんだんと楽しんで描いている事に気が付きました。」
「心理学から見た楽しみの意義」 岩田 昇
「ポジティブな感情は人を積極的にし、仕事に取り組んだり、自由時間を使って創作活動に挑戦したりと、より良い生活の質(Quality of Life, QOL)の実現に関連すると言われています。」
「電動車椅子で鉄道旅行」 麸澤 孝
「電動車椅子で旅行していると、トラブルも少なくない。ホームにおりるとエレベーターが故障中で仕方なく大きな電動車椅子ごと階段を持ち上げてもらったこと。ホテルに車椅子ということが伝わっていなく居室のドア幅が狭く急遽、別のホテルに泊まったこともあった。行き当たりばったりでの旅行はそんなこともよくあり、それらも「楽しみ」に感じられることも公共交通機関利用の醍醐味のひとつである。」
「勝負の世界に飛び込め!!」 中野 勇輝
「私は生まれつき筋ジストロフィーという全身の筋肉が萎縮していく不治の病に侵されながらも、普通校の高校に進学、ドイツ留学、自伝本「ユウキノシルシ」の出版、電動車椅子サッカー日本代表に3度選出など、数々の夢を実現させてきた。かつての私がそうだったように、もしあなたが今現在、自分の障害に劣等感を抱いているならば、これから前向きな心を手に入れ、人生をより良くしてほしいという想いを込めて、私の経験から学んだことをお話したいと思う。」
「もう一度大空へ −障害者にも空を飛ぶ楽しさを!−」 平野 功
「障害者が航空機のパイロットになったり操縦の練習をしようとすると、法律上のハードルが高いだけでなく、手や足に麻痺があれば、そもそも操縦できる機体がないのが現状である。・・・ラジコン機をそのまま大きくして座席を乗せ、電動車いすを操作するようなジョイスティックを使って操縦できれば、重度の障害者でも機体の操縦ができるのではないかと考えたのである。」
「バークレイ遊学」 貝谷 嘉洋
「自立生活により重度の障がい者として生きるすべを学び、大学院の修了により実学を身に着けた。そして、バークレイ生活の締めは、アメリカ一周という「遊び」である。日本では自分が運転できるなんて、考えも及ばなかった。ところがアメリカでは私のような重度の障がい者でも、運転できる車があった。その名もジョイスティック車。棒状の運転装置を前後左右に倒すことによって運転ができる。」
「絵画制作をいきる糧に」 古小路 浩典
「リハビリの一環として始めた絵画制作は、こうして継続する内に幸運にも結果職業となり、主に文房具・ポスト
カード・カレンダー等のイラスト制作の仕事につながることになった。現在は、各地で開催される絵画展でのワークショップや講話活動を取り入れたプログラムを『口と足で描く芸術家協会出版社』主催のイベントとして行っている。」
「DJ を楽しむ」 岡田 健司
「ときは過ぎ、親元から離れて一人暮らしを実現した。先天性ミオパチーという障害とそれに付随する呼吸器障害ゆえに人工呼吸器とともに地域生活を始めた。保護者がおらず、呼吸器管理を自らおこない、夜間ヘルパーもつけずに自立した障害者はいまとしてもめずらしい事だった。一人暮らしを始めて自分自身のことを理解してもらうために多大な時間を割かなければサポートが得られなかった時期が過ぎ去り、ふとしたタイミング、あたかもそれは暖かい日差しを受け硬い地面から芽吹くタンポポのように自然と身についていた教養が溢れ出してきた。DJ がしたい。」