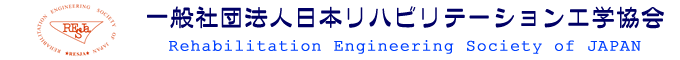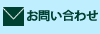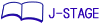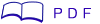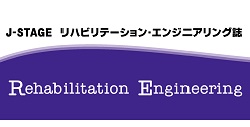協会誌Vol.30/ No.2 (通巻98号)
特集「30巻記念号 これ(明日)からの30年」
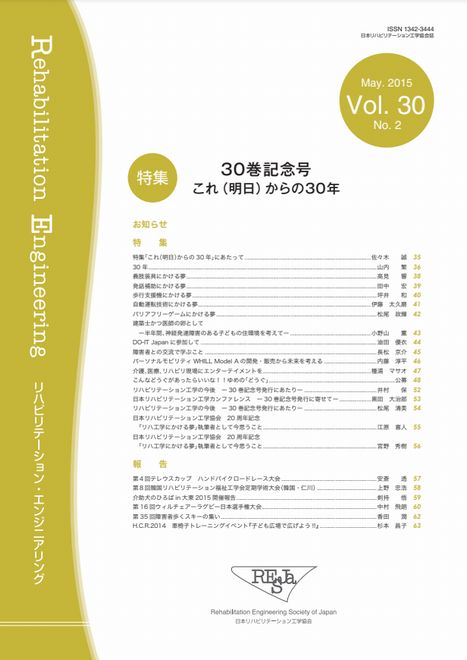
「特集「これ(明日)からの30年」にあたって」 佐々木 誠
「「本日をもって、日本リハビリテーション工学協会を解散します」そう言える日が来るとすれば、どのような技術が生まれ、どのように社会が変化した時でしょうか?」
「30年」 山内 繁
「注目して欲しいことは、介護保険の福祉用具は、利用者が「自己責任」で、用具を自由に選択・返却できるという希有なシステムである点です。高価なロボットは消毒経費も含めて貸与事業者が大きいリスクを背負い込むことになります。」
「義肢装具にかける夢」 高見 響
「3 次元動作解析システムの活用は、動作の記録と多面的な表現で記録した動作データを再生可能とするため、作業療法士による動作観察・評価を補うこととなり、その使用効果は大きい。」
「発話補助にかける夢」 田中 宏
「発話補助のための音声合成システム<夢>は、音声をユーザのイメージ通りにユーザの口から出力するシステムである。」
「歩行支援機にかける夢」 坪井 和
「人は歩けるようになると、走りたくなる。ACSIVE の研究・開発に携わる中で、走ることも支援できるようにして欲しいという要望が多くあった。」
「自動運転技術にかける夢」 伊藤 太久磨
「現在の技術がこのまま進化していけば、どこかのタイミングで完全な無人運転は実現する。しかし、もはやそれはロボットタクシーへの乗車であり、自動車の運転ではなくなってしまう。」
「バリアフリーゲームにかける夢」 松尾 政輝
「視覚障害者と健常者がともに楽しむことができ、同じゲームの話題を共有することは、両者のコミュニケーションを促進する一つのきっかけになるのではないでしょうか。」
「建築士かつ医師の卵として ー半年間、神経発達障害のある子どもの住環境を考えてー」 小野山 薫
「「発達障害」と一口に言っても、子ども達は多種多様で個別対応が必要であること、明るいお母さんもいれば憔悴しきったお母さんもいること、子どもの安全確保や親のストレス軽減には住環境整備が有効であるが、まだ十分に認知されていないこと等、支援の実情を現場で学ぶことができた。」
「DO-IT Japan に参加して」 油田 優衣
「DO-IT を機に、パソコンを利用することで体への負担が減ることを知り、実際に私は、二学期から学校でパソコンを使用してノートテイクをするようになった。」
「障害者との交流で学ぶこと」 長松 京介
「私がこの仕事を体験して思うことは、利用者様と介助者がWin-Win の関係が大切だということです。」
「パーソナルモビリティWHILL Model A の開発・販売から未来を考える」 内藤 淳平
「例えば、観光地や商業施設などにシェアできるモビリティが備わっていれば、車や電車での移動に対し、制約が少なくなり、金銭面での負担も軽くなる。パーソナルモビリティのシェアリングが新しい交通インフラとなる可能性を感じている。」
「リハビリテーション工学の今後 ー30巻記念号発行にあたりー」 井村 保
「この地域には本邦における主要な車椅子メーカやリフトメーカ等があるものの、まだまだリハ工学を
知らない人も多いのではないだろうか。」 注.この地域:中部支部
「日本リハビリテーション工学カンファレンス ー30巻記念号発行に寄せてー」 黒田 大治郎
「近年の福祉機器への関心と理解、研究開発、供給普及は30 年前の比ではなく、かつての予想をはるかに超えるすさまじい早さで日常生活に浸透し、拡大拡張が進んでいる。」
「リハビリテーション工学の今後 ー30巻記念号発行にあたりー」 松尾 清美
「我々は障害者や高齢者の身体や生活方法を知った上で、様々な専門職と共同して福祉機器を開発することが、被介護者の生活や就労環境改善のために、最も望まれていることと考えています。」
「日本リハビリテーション工学協会 20周年記念「リハ工学にかける夢」執筆者として今思うこと」
江原 喜人
「支援技術に関する情報の集約や体系化を行うこと、それらの情報を当事者やその家族、関わる多くの職種で議論し共有すること、それらの情報を発信して現場で活かしていくことの重要性を改めて感じます。」
「日本リハビリテーション工学協会 20 周年記念 「リハ工学にかける夢」執筆者として今思うこと」 宮野 秀樹
「やはりこれからも夢を語りたい。どんなに重度の障害があろうとも、理想や夢を語り続ける、諦めることなどない社会作りに尽力したい。」