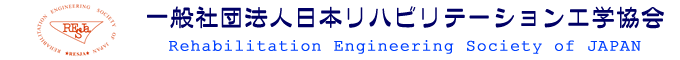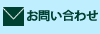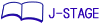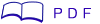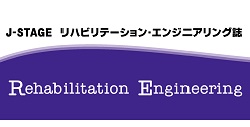協会誌Vol.29/ No.4 (通巻96号)
特集「障害者差別 −知る・向き合う・取り払う−」

「特集「障害者差別 −知る・向き合う・取り払う−」にあたって」 油田 あゆみ
障害者差別解消法成立に伴い社会全体が変化しようとしている今、障害者差別とは何なのか、障害者差別解消法成立に至った経緯とその内容、そして動向もふまえ、障害者差別について知る契機になってほしいと願い今回の特集とした。
「容貌障害について考える」 藤井 輝明
「かつて私は、「藤井の腫れた、膨れた右血管腫顔に触れると、手が腐る、とける」といった噂やデマを流された体験があります。そこで、実際にふれてさわってタッチングしていただくと、こうした噂やデマがいかに無責任なものかが交流会に参加していただいた方々によくご理解いただけるわけです。」
「「障害者差別解消法」成立までのあゆみ −身近な場(地域)から共生社会の創造を目指す法の誕生−」引馬知子
「差別解消法は、以上の差別の物差し等の提示、及び、苦情申し立てや救済の窓口の明確化を前提に、当事者が、合理的配慮を求める意思の表明を行う等、日々の社会的障壁を示してこそ本来の意味を発揮する。このため、社会は、意思表明が難しい障害のある人々に最大限の支援を行う必要があろう。」
「障害者差別解消法の意義と課題」 廣田 久美子
「この法律では、行政機関等及び事業者の障害者に対する「障害を理由とする差別」として、「不当な差別的取扱い」と「合理的配慮を行わないこと」の二つの類型を規定している(7 条、8 条)。」
「障害者差別解消法の施行に向けて」 加藤 誠実 小田 亜由子
「法律の名称はその内容を最も端的に表しているものであるが、実は、この法律の名称は検討の段階で、当初、差別「禁止」法であったところ、差別「解消」法に変わった。それは、この法律が、行政機関や事業者等における障害を理由とする差別を禁止するとともに、それを社会において実効的に推進するための基本方針や指針の策定等の措置や、相談・紛争解決の体制整備等の国や地方公共団体における支援措置についても定めており、これらを通じて差別を「解消」し、差別のない社会を目指すものだからである。」
「イギリス障害差別禁止法理の形成と課題 −2010年平等法を中心に−」 杉山 有沙
「本稿は、平等法を素材に、イギリス障害差別禁止法理の形成と現状を検討してきた。同国の法理の根底にあるのは、障害者が抱える障害による不利の責任を社会側に見出す視点である。この視点は、日本においても共有されるものである。」
「障害者スポーツの中にあるカテゴリー −障害を持つ者のAlpine Ski(チェアスキー)−」 井上 英年
「現在の日本には、世界には存在しない頚髄損傷者のチェアスキーAthlete を生み出すことが出来る世界最高水準の道具と、指導プログラムが存在し、世界のシットスキー界(チェアスキー)を牽引している。」
「「差別」を減らすために」 大西 瞳
「「何かあったら責任が取れない」と言われると、答えが先にあって、叶える為の検討がされていない印象を受けてしまう。ここでお願いしたいのが、先ず本人の要望を極力叶える方向で考えて欲しいと言う事。」
「「差別」と感じるものと自分なりの向き合い方」 野田 隼平
「実際、股義足で走り、陸上の試合に出場している選手は、現在世界でも私一人である。世界に参加選手が一人では、競技人口が少なすぎて競技として成立しない。股義足のクラスが存在しないことは、「差別」ではなく、「現実的な判断」であり、やむを得ないことなのである。」
「視覚障害を抱えて生きる」 中村 達男
「視覚障害が重度になった反面、私の生活の質は向上した。白杖を持っていなければ、当然ながら誰も私に声をかけてくれない。見えていないのに、いかにも見えているように振る舞う私の行動が、かえって不自然に見られ、人に誤解され、不審者扱いされたこともあった。思えば、自らの状況を表示し、伝える努力・勇気が足りなかったのだ。」
「差別・偏見を越えてゆく進化力」 松嶺 貴幸
「この「自分が進化する」というアイディアをアメリカから持ち帰った。2011 年5 月、1 年間の留学生活を終えて日本に戻り、ランプアップいわてという活動を発足させた。翌年10 月には一般社団法人ランプアップいわてとして法人化。スロープ(ランプと名付けた)を制作し、段差のある店舗や施設に寄贈し、段差を自分たちで一つ一つ減らしていく取り組みだ。」
「大学における障害学生支援の現状と課題 −筑波大学障害学生支援室の取り組みを通して−」 竹田 一則、名川 勝、有海 順子、森 まゆ、青木 真純、田原 敬
「OSD の特色は、第一に一定のトレーニングを受けた有償ボランティアの「ピア・チューター」と呼ばれる学生が、支援の中心を担うことである。障害学生自身もピア・チューターとして参加し、学生たちが主体的に支援活動を展開している。それらの活動を通じて、障害の有無に関わらず、全ての学生が共に成長できる体制を目指している。」
注.障害学生支援室(Office for Students with Disabilities: OSD
「東横インのユニバーサルデザインへの取り組み」 猪股 和明
「これまで日本のサービス業は、「できないこと」をあいまいにしつつ、現場ごとで対応する傾向がありましたが、東横インではホームページ(以下、HP)でできないことを明記することにしました。…。その間の障がいのある方の宿泊は、2008 年度(4月− 3 月)で8841 人でしたが、2013 年度は24,088人と約3 倍にもなっています。」
「障害を価値と捉えるバリアバリュー視点が生む企業価値」 垣内 俊哉
「このバリアバリューという考え方は、弊社のスタッフの経験から生まれた。例えば、車いす利用者の目線の高さは、約100 センチである。その高さだからこそ、気づくことや見えることがある。全盲であるからこそ、紙媒体の資料を読み取ることは困難でも、声による感情の変化や呼吸を読み取る能力に長けており、電話対応を得意とするケースもある。」
「高等教育機関における合理的配慮の現状と今後」 近藤 武夫
「一部で充実した支援の取り組みがある一方、その他の大学では差別的取り扱いや排除がそのままになっていることが日本の特徴であると言える。差別解消法の施行後の、全国の教育機関の動きに注目する必要があるだろう。」
「障害者差別解消法成立から考える −交通権をめぐる活動より−」 後藤 昌男
「車椅子や白杖が必要な障害者にとって、積雪期の社会参加は極めて厳しい。昨年の冬は特に大雪だったため歩道の除雪が追い付かず、電動車椅子の通勤者が已む無く危険を冒し車道を移動している実情が北海道新聞に報道され、市民の反響をよんだ。」
「障害者差別(解消法)と工学」 松尾 清美
「40年前のこと、復学したいと大学へ申し入れしたところ教授会が開催され「車椅子を使っての生活は大変だし、単位がとれないなどの理由で自殺などされても困るから復学は認められない」と言われ、教授会に出席した叔母の「このことを新聞に公表しますが宜しいですか?」という言葉で、数時間後には復学することが認められたのである。・・・。様々な工学技術で様々な福祉機器を開発し、障害者への合理的な配慮を促進して、その方の人生を支援していくことが、エンジニアに求められている。」