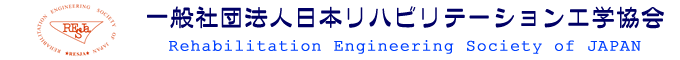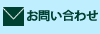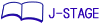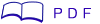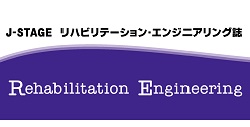���Vol.29/ No.2 (�ʊ�94��)
���W�u���S�Ɉ��S���Ďg�������邽�߂Ɂi�Ԉ֎q�ҁj�v

�u���W�u���S�Ɉ��S���Ďg�������邽�߂Ɂi�Ԉ֎q�ҁj�v�ɂ������āv�@�А@�C
�u�������]�Ԃ��p���N�����玩���Ŏ��]�Ԃ������Ď��]�ԉ�����ɍs���C������Ē����Ă��炤�B���퓖����O�Ƃ���Ă�����i�ł���B�Ƃ��낪�Ԉ֎q�ƂȂ�ƂȂ��Ȃ����܂�����Ă����Ȃ��̂������ł���B�v
�u�����p��Տ��I�]�����Ƃ̊T�v�|���S�Ŏg������̗ǂ������p��̊J���E���y��ڎw���ā|�v�@���@�R����
���v���c�@�l�e�N�m�G�C�h����ł́A�����p��̈��S�ȗ��p���m�ۂ����̂�h�~���邱�Ƃ��i�ق̉ۑ�ł���ƍl���A�����J���ȂƘA�g���āu�����p��Տ��I�]�����Ɓv��21 �N�x�����{���Ă���B
�u�Ԃ������S�����m�̈琬�v�@��@���Y
�u�����p����ʂ�����A�܂����ҁE���p�Ҏ��_�Ō����w���E�����^����̈��S���m�ۂ͂ǂ̂悤�ɒS�ۂ���悢�̂��낤���B���̓����Ƃ��ē����o�������̂��A�����p��ʌ�̈��S����S�ۂ��邽�߂̐l�ވ琬�ł���B�v
�u�u�Ԃ����E�V�[�e�B���O����Z�\�{���R�[�X�v�̎��g�݁v�@���V�@��Y
���ǂ������p��T�[�r�X����邽�߂ɕK�v�ȁu����ɂ�������H�́v��L����l�ނ�y�o���邱�Ƃ��ӎ����āA�R�[�X�ڕW�����̂悤�ɐݒ肵���B
�w����ҋy�я�Q���E�҂��g�p����u�Ԃ����E�p���ێ����u�v���̕����p��Ɋւ����w�I�E�H�w�I��
��I�m�����w�ԂƋ��ɁA�����@��̐���E����ł̒����E�C���E���Njy�ъe�푊�k�����ł�����H�I
�Z�p�҂܂��̓t�B�[���h�G���W�j�A�ƂȂ肤���{�I�ȋZ�p�E�Z�\���K������B�x
�u�{��w�Z�ł̎Ԃ��������e�i���X�̎��g�݁v�@���ځ@�Α�
�Ԃ��������e�i���X�̎��g�݂��s���Ă���m�I��Q���畔�卂�����i�{�Z�j�́A����15 �N�ɕ��u����A11 �N���o�悤�Ƃ��Ă���B
�u�����e�i���X�̌���|����������S�E���S�̎Ԉ֎q���l����|�v�@����@�P�L
�u�ł��邩����A�����̑̂̈ꕔ�ł���u�Ԉ֎q�v���n�m���Ē����A�����̃����e�i���X�y�ыً}�����̓��[�U�[���g���ł���悤�ɂȂ��ė~�����v
�u�����e�i���X����i������Еҁj�v�@���@����
�u�Ԉ֎q�𗘗p���������O�Ɉ��S�Ɏg�p���邽�߂ɋ�C���̃`�F�b�N�͕K�v�ł���A��C�����K���łȂ��ƃp���N�̌����Ɍq����܂��B�܂��Ă�A�^�C���̋�C�������Ȃ���ԂŎg�p����ƃp���N�͂������̂��ƁA�u���[�L�̃��b�N���ł��Ȃ��Ȃ�A�Ԉ֎q���������肵�Ď��̂̌����ɂ��Ȃ�܂��B�v
�u�����e�i���X����i�̔��X�ҁj�@�v�@�����@����
�u�o���C���́A�قƂ�ǂ̏ꍇ�A��x�K�₵�Č��Ԃ��m�F�����i����肷��K�v�����邽�߁A�R�����ړ����ԁA�~���͐ϐ�⎋�E�s�ǁA�H�ʂ̓����Ȃlj^�]���X�N���l������ƁA�s�̎Z�����m�̏�ōs��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�v
�u�����e�i���X����i�̔��X�ҁj�A�v�@�{���@����
�u���̑Ή��N����6 �N�ƐL�тĂ��Ă���ɂ��ւ�炸�A����_�����̋`���t���͂Ȃ��A�j�������ɋC�t�����Ɏg�p����Ă���P�[�X�����Ȃ��Ȃ��B�v
�u�����e�i���X����i�̔��X�ҁj�B�v�@�k���@�L��
�u�Ԉ֎q�͎����ԂƈႢ�Ԍ����Ȃ��B���̏ꍇ�A�����p�҂̑����͌̏Ⴗ��܂Ŏg�������A���̌�A���������������Ƃ��قƂ�ǂł���B�v
�u�����e�i���X����i�̔��X�ҁj�C�@�Ԉ֎q�𑫂Ƃ��邽�߂̑����ɂ��ď��X�v�@�吼�@���o�a
�u����t�����ė~�����̂���ԗւ̒E���@�\�ł���B�ԍڂ̍ۂɕ֗��Ȃ͓̂��R�����A�Ԉ֎q�̌̏�̑唼���߂�p���N�C���̍ۂɂƂĂ��𗧂��炾�B�E���@�\������Ύԗւ������O���Ď��]�ԉ������o�C�N������Ɏ������݂��ł���B�v
�u�����e�i���X����i�̔��X�ҁj�D�v�@�R��@��K
�u���݂̐��x��C���͕��i��ɂȂ��Ă���B�o�c�I�ɕ��͂���Ǝ��ł����ƐV�K65���ɑ��āA�C����35�����x�ł��邪�A���㍂�ł݂�ƐV�K90���A�C��10���ƂȂ�A���Ȃ�A���o�����X�ł���B�v
�u��Q�Ҏ{�݂ɂ�����Ԃ������S�Ǘ��̌���Ɖۑ�v�@���X�@��
�u���p�Җ{�l�Ƃ��̉Ƒ��A�����ɌW���E�����Ԃ����̋@�\�𗝉�������Ă��Ȃ����Ƃ��A���Ǝ҂͒m��ȉ߂���Ɗ����܂��B�v
�u�u������E�Ԃ����v���W�F�N�g�v�����܂��܂Ł|�p�L�X�^���Ƃ̗��j�|�v�@�֓��@��
�u�u������v�̏��܂�́A2002 �N���̃_�X�L���O�����Ƃ��Ĉ�N�߂��̌��C���I���A�����߂Â����p�L�X�^���̃V���t�B�b�N���̌��t����ł������B�u�A����������{�Œm���������̊T�O�ŃZ���^�[��n��A�����ē��{�ŏ�����A�N�e�B�u�ȎԂ��������A��������ΏႪ���҂̌�������Ες��v�E�E�����������e�ł������B�E�E�E�p�L�X�^���̓����ҒB�͗͂����킹�傫�ȃ��[�u�����g���N�����n�߂Ă���B
�ނ炪�����������x���v�́A�@�Ԃ����̌�t���x�̐����A�A���ÎԂ����͗A���o���Ȃ��i�ڂł������A���̐��x����O�����{���\�������A�B�p���W���u�n���̑�w�ɒʂ��Ⴊ���҂ɂ͓d���Ԃ������x�������Ƃ������{���\�E�E�E���X�B�v
�u���@�\�d���Ԃ��������S�Ɏg�����߂Ɂv�@�����@�N��
�u�ǂ�Ȃɍ����@�\�̗D�ꂽ�d���Ԃ����ł��V�[�e�B���O���g������ɍ���Ȃ��Ƃ��ɂ́A��邱�Ƃ̏o���Ȃ��Ԃ����ƂȂ�B���N�g�p���Ă�������̎Ԃ����̃V�[�e�B���O�ɕ����o���邩���A�V�����Ԃ����ɏ�芷����ׂ̍ŏd�v�_�ƂȂ�B
�a�C�̐i�s�ɂ���āA�ς��̂̏�Ԃɍ��킹�āA�lj��ŋ@�\��lj������邱�Ƃōŗǂ̎Ԃ����ƂȂ�ꍇ������B�v
�u�m���E�F�[�̎Ԉ֎q�����e�i���X����v�@�ؔV���@���A���@�O
�u�m���E�F�[�Љ�͕������d�����Ă���A�l���⌠������邽�߂ɏ�Q�ɊW�Ȃ��A�⏕���₻���ɂ������p�͖����ŁAIT �Ȃǂ̎x���@����܂߃T�[�r�X�̎��͂��ׂē��ꂳ��Ă���B�v