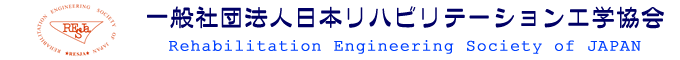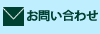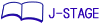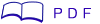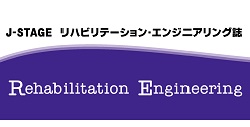協会誌Vol.29/ No.1 (通巻93号)
特集「私の手になる道具たち」

「特集「私の手になる道具たち」にあたって」 鈴木 太
「昨年子供を授かりましたが、自分の手にもどかしい思いをしています。泣き叫ぶ子供を前に何も出来ず、目の前にあるおもちゃでさえ渡すことが出来ません。つかめたら…、日頃からつかむことに大きな夢を抱いています。」
「つかみ・つまみ・なやみ」 油田 あゆみ
「狩猟生活でヒトは道具を使うことを覚え、さらに道具を作り使用するようになった。この時、最初に作り出したとされる道具は、獲物の皮を切る(裂く)道具と言われている。これを人間の手でできなかったため、道具(石器の原型)ができたのである。道具は人間の手ではできない働きを補うものであり、それは人間が生活をしていくための支援機器ともいえる。」
「“つかむ”自助具ー自立生活を支えるものづくりー」 岡田 英志
「自助具を使いこなすためにはそれなりの努力や気力を要する。自ら困難に立ち向かい解決したいと思う気持ちが大切であり、自助具を使うことによって自立生活への意欲が醸成されることが一番の効果と言えるのではないだろうか。」
「装具−把持装具、ポータブルグリッパー−」 片本 隆二
「本稿では、ポータブルグリッパーの開発経緯を研究の流れ(聞き取り調査、紙バンドを用いた試作、院内連携による評価)に沿って報告するとともに、多目的ロボットアームへの展望についても言及する。」
「生活支援ロボットHSR(Human Support Robot)」 池田 幸一
「手がかりとしたのが、四肢障がい者のサポートを行っている「介助犬」である。日本介助犬協会の協力のもと、介助犬に関する調査に、ロボットに対する質問事項を加えて、アンケートを実施した。その結果、日々の生活サポートにロボットを使うことに対する受容性は高く、そこでの期待する機能として、「落ちたものを拾う」、「指示したものを持ってくる」、という意見を得た。」
「ユーザーの腕となるロボット:アイ・アーム」 島田 真太郎
「例えば飲食はもちろん、かゆいところを掻く、屋内や玄関のドアを開けるといったこともできる。アイ・アームは介護ではなく、ユーザー自身で操作する自立を目的としたロボットで、この分野では世界で初めて実用化されたものである。」
「ロボットアームのコスト・ベネフィット評価」 井上 剛伸
「介助時間を尺度とした機器の価値についての主観評価の結果からは、機器の価値が機器導入価格に見合うとするユーザーがいる可能性が示された。ただしその一方で、ロボットアームの導入により、現在の介助サービスの利用時間を減らすことができるかについては、否定的な意見も得られた。」
「当事者体験 「パートナーロボット」」 鈴木 太
「ロボットと人の手の使い分けによって、ユーザーが一番心地よい形にパートナーロボットをどう活用するかはこれからのユーザーにかかっていると感じました。」
「「生きた補装具」介助犬」 高柳 友子
「介助をしてもらう、というだけでなく、「犬」という一つの命を引き受ける決意をすることが、介助犬導入をするということでもある。これが、道具と最も異なる点であろう。」
「当事者体験 「介助犬」」 鈴木 太
「担当者の方から介助犬に対して行う指示を教えていただきました。基本のテイク(くわえて)とグッド(よし!)です。…。グッドと声をかけながら頭をなでます。膝に顔を埋めてうれしそうな笑顔を返してくれました(写真1)。」
「オットーボック社の筋電電動義手マイオボックについて」 八幡 済彦
「筋電義手は、その筋電を利用してスイッチを入れ、バッテリーの電流をモーターに送って手先を動かす電動義手のことである。マイオボックは、筋電義手としてだけではなくスイッチを使った電動義手としても使用可能なシステムである。」
「当事者体験 「筋電義手」」 鴨治 慎吾
「筋電のシステム自体はとても反応が良かった。義手は握る、開くといった操作が想像以上に容易であった。力加減により握る速度等を調整することもできた。切断等で義手を使う方にとってはとても良い物だと思う。」
「助けられる手から助ける手へ」 鈴木 太
「そんな時、妹からスイングベットが届きました。「これならいけるか!」力のない右手で押してみます。揺れている…。気をよくしてあちらこちらに滑り止めを貼り付け特製スイングベットの完成です。毎日リハビリのように揺らし続け、はじめて寝付いたときの感動は忘れられません。自助具に子供を近づけ、私のスプーンで一口を食べさせたときは、言葉に出来ない感覚でした。」