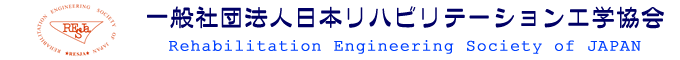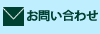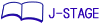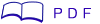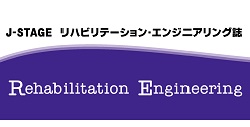���Vol.28/ No.4 (�ʊ�92��)
���W�u��a�ƃ��n�H�w�v
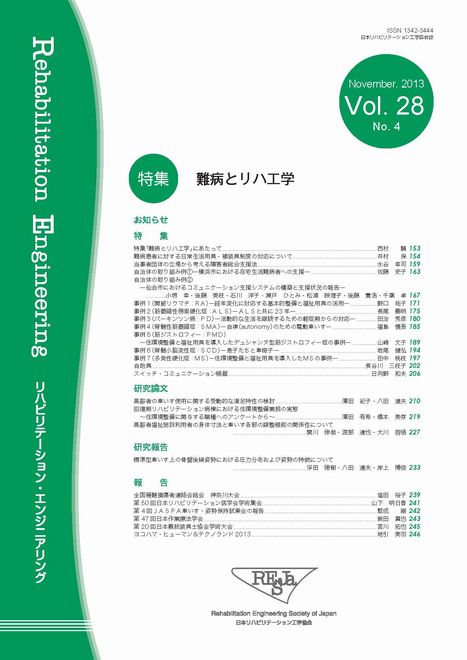
�����W�u��a�ƃ��n�H�w�v�ɂ�������
���� ��
2013�N�{�s���ꂽ�u��Q�ґ����x���@�v�ɂ����ď�Q�҂̒�`�Ɂu��a���v���lj�����A�K�v�ƔF�߂�ꂽ�����T�[�r�X�������p�ł���悤�ɂȂ����B���̋@��Ƀ��n�H�w�̕���ʼn��߂āu��a�v���L�[���[�h�œ��W��g��ł݂����Ǝv�����B
����a���҂ɑ�����퐶���p��E���x�̑Ή��ɂ���
�䑺 ��
�u��a���ғ������p�ł����Q�����T�[�r�X�Ƃ��Ă̕����x�����x����퐶���p��t���x�̗��p�\��������ہA�܂��A���̔��蓙�̑Ή��ɂ����闯�ӎ������J�݂���ƂƂ��ɁA����̉ۑ�ɂ��Ă����y����B�v
�������Ғc�̗̂��ꂩ��l�����Q�ґ����x���@
���J �K�i
�u��Q�̒�`�Ǝ���@�ɂ�����ΏۊT�O�̓W�J�̌o�߂��ӂ܂��āA�����Ғc�̗̂��ꂩ���Q�ґ����x���@�ɂ�����Ώ۔͈͊g��̂��Ӗ��Ƃ��̐��x��̈ʒu�Â����m�F����ƂƂ��ɁA��a�Ⓑ���������������l����Q�ґ��������@�ɂ������Q�����T�[�r�X�����p���邤���ŗ��ӂ��ׂ����Ƃ��q�ׂ�B�v
�������̂̎��g�ݗ�@�@�[���l�s�ɂ�����ݑ����a�҂ւ̎x���[
���� �j�q
�u��a�҂ɑ���x���ɂ��āA���l�s�ɂ������g���Љ��B���l�s�ł́A���ǂ���Љ�A�܂ł̈�т������n�r���e�[�V�����̓W�J��ڕW�ɒn��x���V�X�e�����\�z���Ă����B�v
�������̂̎��g�ݗ�A�@�[���s�ɂ�����R�~���j�P�[�V�����x���V�X�e���̍\�z�Ǝx���̕[
���� �K, �㓡 ���}, �ΐ� �m�q, ���� �ЂƂ�, ���Y �f���q, �㓡 �M�_, ��t ��
�u���s��Q�ґ����x���Z���^�[�́A���ƌv��u�A�N�V�����v�����v�Ɋ�Â��āuALS���̃R�~���j�P�[�V��������҂ɑ��āA������Q�̌y������̎��iQOL�j�̌����}�邽�߁A�ӎv�`�������p�����R�~���j�P�[�V�����m���̂��߂̎x�����^�C�����[�ɍs���x���V�X�e���\�z��}��v���ƂɎ��g��ł����B
������P�i�߃��E�}�`�F�q�`�j�@�[�o�N�ω��ɑΉ������{�I�����ƕ����p��̊��p�[
��� �S�q
�u���Â̌��ʂ�Ǐ�̕ω������z���Ăǂ��������Ă����̂��A�e���C�t�X�e�[�W�ŕK�v�Ƃ���鐶������A����ɂ͐����̎����ێ��A���コ���邽�߂̃��n�H�w�̂�������������邽�߂̂ЂƂ̑�ނɂȂꂽ��K���ł���v
������Q�i�؈ޏk�������d���ǁF�`�k�r�j�@�[�`�k�r�Ƌ��ɂQ�R�N�[
���� �`��
�ٕ̂̈ρA���m����A���@�A�ݑ�Ɉڂ�A��p�����ł����A�G��`���n�߂�A���n�r���Ƃ́A�����ȃ��n�r���ɂ��čׂ����Љ�A�M�҂�23�N��U��Ԃ�A�͋����u���͎̂Ă���̂ł͂Ȃ��B���ʂ܂Ŏ�����������̂ł���B�v�ƂÂ��Ă���B
������R�i�p�[�L���\���a�F�o�c�j�@�[�����I�Ȑ������p�����邽�߂̌y�NJ�����̑Ή��[
�c�� �G�F
�u�p�[�L���\���a�͊ɏ��ɐi�s���鎾���̂��߁A��������c�����āA“�^�C�����[�ȃA�v���[�`”��“�p���I�ɍs��”���Ƃ��]�܂����B�v��������グ�ďЉ�Ă���B
������S�i�Ґ����؈ޏk�ǁF�r�l�`�j�@�[�����iautonomy�j�̂��߂̓d���Ԃ����[
���� �T��
��Q�����ɍ������@��I�т���x������̗���܂ŏڍׂɕ��Ă���B�܂��A�����ʂ��Ď����̂��߂̓d�����t�g�@�\�̕K�v�������q�ׂĂ���ӌ������Љ�Ă���B
������T�i�W�X�g���t�B�[�F�o�l�c�j�@�[�Z�������ƕ����p��������f���V�����k�^�W�X�g���t�B�[�ǂ̎���[
�R�� ���q
15�Βj�q�̎����ʂ��āA�uDMD�ɑ���Z�������ƕ����p����̃^�C�~���O�ɂ��Č��������̂ŕ���v
������U�i�Ґ����]�ϐ��ǁF�r�b�c�j�@�[���q�����ƎԈ֎q�[
��� ���O
�Ԉ֎q�̓����o�܂⎩��̉��z�Ȃǎ��n��ŕ��A��l�̑��q�����̐����ƉƑ����J����Ă���B
������V�i�������d���ǁF�l�r�j�@�[�Z�������ƕ����p��������l�r�̎���[
�c�� ���}
�u�@�\�ቺ��悵��MS�̎���ɑ��A�މ@����Ƃ��̌�̒P�g�����̂��ꂼ��̎����ɂ����āA�Ǐ�̕ω��ɍ��킹�Ȃ���A�����p��̓���������������{�����ۂ̂�������x���̃|�C���g�ɂ��ĕ���v
��������
���J�� �O�}�q
�u2010�N���E�}�`�����v�̃f�[�^���ڍׂɕ��A������𗘗p���銳�҂̐����f�ڂ��A��������퐶������������ւƂȂ���������傫�����Ƃ��q�ׂĂ���B
���X�C�b�`�E�R�~���j�P�[�V�����@��
������ �a�v
�X�C�b�`�E�R�~���j�P�[�V�����@��̕K�v���Ǝ�ނ��A�������Љ�Ă���B�����ɕK�v�ȃL�[�p�[�\���̑��݂���l���E��������̌���ێ��Ȃǎ��p�I�ȋ@�퓱���̎����ʂ��ĕ��Ă���B