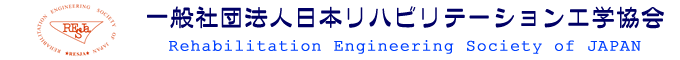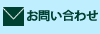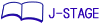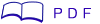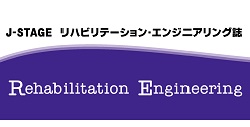協会誌Vol.28/ No.1 (通巻89号)
特集「ICFとアシスティブプロダクツ」

■特集「ICFとアシスティブプロダクツ」
岡田 裕生
「ICFとアシスティブプロダクツ」にあたって
「ICFの中にアシスティブプロダクツとして自立支援機器が明記されている事は分かったが、「実際にICFをどのように活用していくのか」という点に関してはなかなか理解が困難であった。(略)チームアプローチが様々な方面から提唱されているが、チームアプローチを行うためには、共通のツールを用いた評価方法での認識を、チームで共有することが不可欠である。」
■ICF(国際生活機能分類)とアシスティブプロダクツ
棟方 哲弥
「ICFを構成する環境因子の中にアシスティブ・プロダクツが明記されたこと、活動制限や参加制約に「能力」と「実行状況」の評価点が採用されたことにより、共通語であるICFの枠組みでアシスティブ・プロダクツを表現できることが示された。(略)個人因子の分類は社会的・文化的に大きな相違があるために分類は見送られており小数点以下第5桁の付加的評価点は、主観的満足度や参与感とされるが、まだ未開発である。」
■特別支援教育とICF
徳永 亜希雄
「学校教育、そして学齢期という特性を踏まえると、「e1301 教育用の支援的な製品と用具(福祉用具):Assistive Products and technology for education」や「e11521 遊びやすさを支援するために改造された、製品と用具:Adapted products and technology for play」に関する期待も大きい。」
■コミュニケーション機器とICF
坂井 聡
「今、手にしたコミュニケーション機器を使いながら、周囲にいる人との間でコミュニケーション成立の経験を繰り返すことが重要なのである。この経験を通して、コミュニケーションすることの楽しさ、面白さ、便利さに気づいていくのである。この経験の場を如何に設定していくのか、これがコミュニケーション機器導入を考える際に大切であることを忘れてはならない。」
■住環境整備とICF
水村 容子
「住環境をはじめとした建築環境の整備に当たってもこれまで欠けていた視点を補う上で、ICFには様々な可能性が存在する。建築領域での研究・実務時の導入を具体化する動きが望まれる。」
■義肢装具とICF
繩井 清志
「個人因子には全体的な行動様式や性格、個人の心理的資質などが含まれるが、義肢や装具は単なる物ではなく、身体の一部であることから個人因子に密接に結びつくことになる。使用する人の生活文化の違いのほか、義肢や装具を使用する時期や年齢、使用期間、使用方法などが使用者の性格や心理に影響することになる。」
■身体障害のある子どもたちにとっての車いす・姿勢保持装置とICF
高塩 純一
「車いすや姿勢保持装置は、服装や子どもの外見と同様、人の目を惹きやすいものであり、“かわいらしく”、また“かっこいいもの”でなければならない。よりステキなデザインであれば、それだけ声をかけてもらえる機会も増え、周囲の人から受ける関わりの総和も増す。」
■ICFにおける電動車いすの解釈について
小林 博光
「身体機能を補完するためのみの視点では無く、移動する目的とその方法や手段に対応した(=環境に適合した)電動車いすを選択し、移動自体を楽しみつつ、目的地での行動も達成しているように感じられる、これぞ、ICFでいうところのプラス面を考慮した支援機器のあり方と言えるのではないだろうか。」